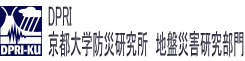- 「 2012年度の活動記録 」
- 2013年3月3~7日
- (独)森林総研・(独)防災科研・日本大学と共同で、新潟県上越市の中山間地帯で現地透水試験および積雪調査を実施しました。
- 2013年1月2日
- 寺嶋准教授の論文がJournal of Hydrologyに掲載されました。
- 2012年11月26日
- 地すべり地に観測機材の設置を行いました。
西井川地すべり地(徳島県三好市)で地盤調査と自然電位観測機器の設置を行いました。千葉大学との共同研究です(電磁気学的手法による斜面崩壊のリアルタイム監視・早期警戒システムの構築)。
パーカッション式ボーリング上から衝撃を加えて、地中にサンプリング管を打ち込みます。当日は深度7mまで掘削しました。 
ボーリングコア深度3mまでのコアです。深度2.5m付近(矢印)で不連続面が見られます。この不連続面は、電気探査で見られた比抵抗が小さな部分と一致しています。 
電極の設置自然電位観測用の電極(塩ビパイプの部分)を設置しているところです 。木製の杭は、ケーブルの配線のために使います。
- 2012年11月21日
- 降雨崩壊実験を行いました。
斜面崩壊に関する水文動態と自然電位変動との因果関係を解明するための、室内降雨崩壊実験を行いました(於・森林総合研究所)
①土層の作成
②土層の作成今回は、下部30cmを密詰め、上部40cmを緩詰めの二層構造で行います。透水係数には3~4倍程度の違いが生じます。 土層(桜川砂)を上部斜面に詰めているところです。土層は10~15cmずつ踏み固めて作成します。その都度サンプリングして、土質試験をします。 
③できあがった実験土層
④計測機器の設置長さ9m、高さ4m、幅1mです。降雨時の土層の変位は、側面に10cm間隔で埋めたマーカーで追跡します。 間隙水圧計(10、40、70cm深)、体積含水率計(10、40、70cm深)、電極(20、50cm深)を、斜面全体に等間隔で設置しているところです。 
⑤降雨
⑥崩壊発生前日に40mmのの事前降雨を与えますが、実験当日の降雨強度は80mm/hです。 降雨開始後70分(総降雨量93.3mm)で崩壊が発生しました。二層構造は、一層構造に比べ崩壊現象が派手に感じます。
- 2012年7月26~29日
- 学生実習で高知県、徳島県の地すべり地の巡検を行いました。
- 2012年6月18~22日
- (独)防災科研と共同で、模型斜面を用いた融雪実験を行いました。
- 2012年5月20日
- JpGUで研究成果を発表しました。
- 2012年4月 1日
- サイトをリニューアルしました。
バナースペース
京都大学防災研究所
地盤災害研究部門
傾斜地保全研究分野
〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄
TEL 0774-38-4117
(研究室 事務室)